
この記事の目次
震災による帰宅困難者の安全を確保するための条例

先日の大阪の地震の際もそうでしたが、
自然災害が起こると必ず発生してしまう問題が鉄道等の運行停止による帰宅困難者の問題です。
まだ記憶に新しい東日本大震災の際も、
東京に帰宅困難者が大量に発生してしまったことが問題になりました。
今後首都直下型の地震が発生した場合、
大量の帰宅困難者が出てしまう可能性が高いです。
また地震によって二次的に発生する火災や建物の倒壊などによる危険も発生する可能性があります。
東京都は震災による帰宅困難者の安全を確保するべく、
『東京都帰宅困難者対策条例』というものを制定しました。
『東京都帰宅困難者対策条例』とは?

改めて、東京都帰宅困難者対策条例というのがどんな条例なのかを簡単にご説明します。
この条例が制定されたのは、平成24年3月で平成25年4月から施行されています。
というものです。
そのために、
震災が発生した直後に一斉帰宅しないように事業者側からの呼びかけや、
待機場所の確保、
その間の食料等の備蓄、
安否確認が出来る仕組み作り
というのを求めた条例です。
結論:会社に備蓄は必要か?

努力義務という形ではありますが、東京都からは従業員の人数に応じた分の備蓄をしておくことを求められています。
ですので、会社に備蓄しておくことが望ましいということです。
なぜ会社に備蓄が必要なのか

会社に備蓄をしておくことが必要な理由は、
従業員の安全確保のためです。
東日本大震災の際もそうでしたが、
震災が起こった後に多くの人が取った行動というのが、
歩いて帰れるところまで帰るということです。
電車が完全にストップし、
バスやタクシーも渋滞によって実質的にはストップした状況で、
帰宅するために取り得る手段というのが徒歩でした。
普段は歩かない距離だったとしても、
頑張れば帰れるという人の多くは歩いて帰ることを選択しました。
ただ、本来は何が起こるか分からない状況の中で街中を歩くというのは非常に危険なことです。
そのため、むやみに動き回らずに会社に待機できるようにし、
その間も最低限の飲食はできるようにするために備蓄が求められているということです。
どれくらい備蓄を準備しておく必要があるのか

色々と対応しておくべきことがありますが、
1つ気になる大きなポイントとして、備蓄をどれぐらいしておく必要があるのかという点があります。
具体的には、飲料水が1日3リットル(合計9リットル)、主食を1日3食(合計9食分)です。
これを従業員の人数分常に備蓄しておくことを求めているということです。
改めてみると、大量の備蓄が必要になるため、
実際に対応できているところと出来ていないところがあるというのが現実のところです。
その他、備蓄をする上での注意点は?

備蓄をするためにはどうしても問題となってくるのが、場所の確保です。
いざ災害が発生した場合に取りに行ける場所に備蓄していないと意味がありません。
ただ、それだけの場所を簡単に確保できる会社というのもそんなに多くはありません。
そのため、備蓄をするために置き場の確保の工夫が必要となります。
また、
ある程度日持ちがするものを用意することと、
消費期限が過ぎる可能性のあるものは、
定期的にチェックをして備蓄を入れ替えすることも必要となります。
「会社に備蓄が必要」のまとめ

その大きなポイントが備蓄で、
社員の安全を確保するためにはしっかりと対応すべきことです。
食料や水分はもちろん、
その他にも懐中電灯や毛布など身を守るために必要なものは備えておくことが必要です。
災害というのは忘れた頃にやってきます。
いざとなった時に出来てなくて困らないように、日頃から意識を高めて準備しておくようにしましょう。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
取り急ぎ御礼申し上げます。
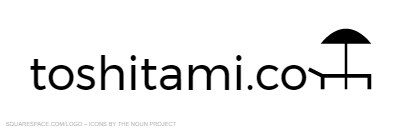
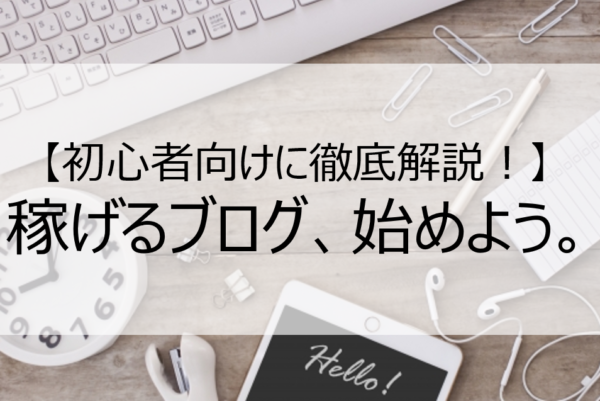
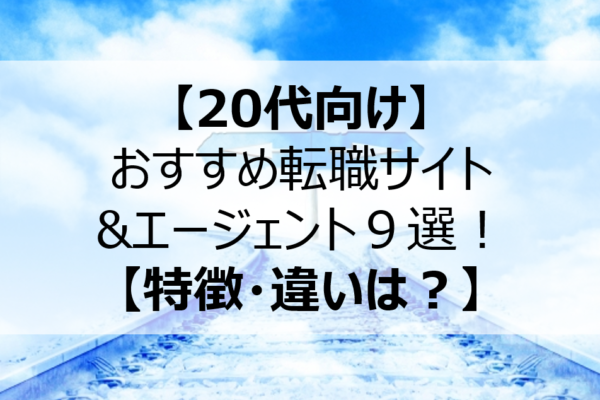
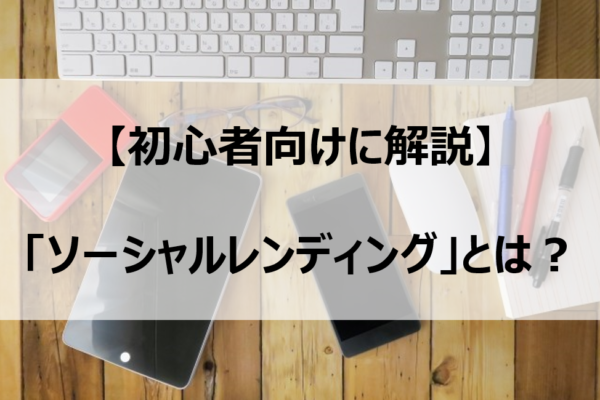

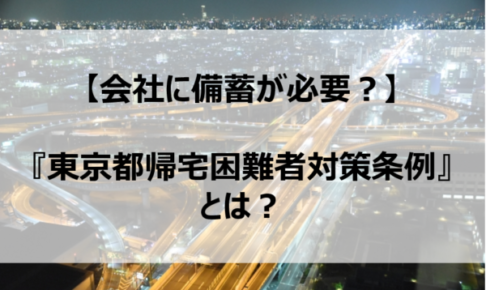



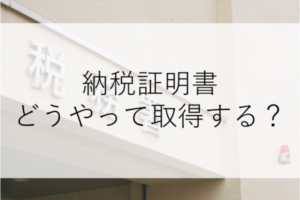


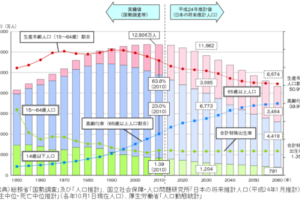




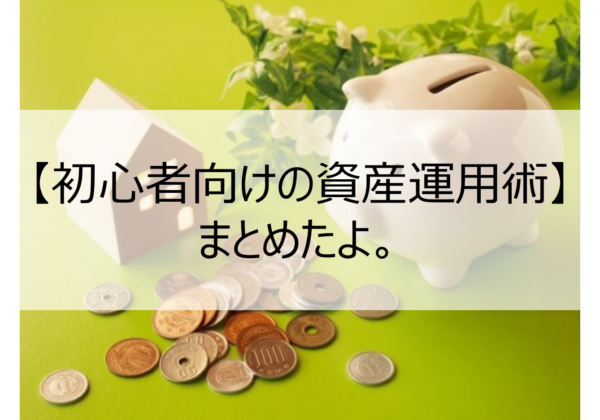
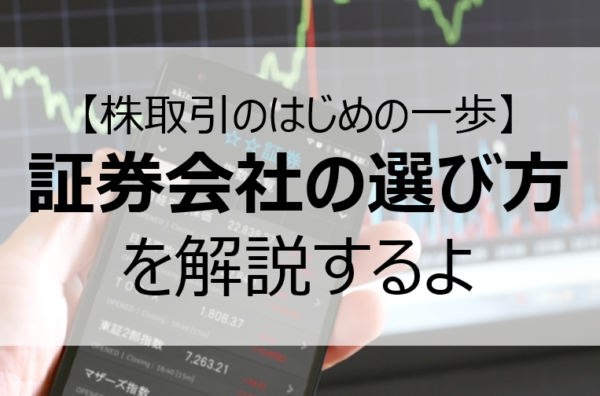

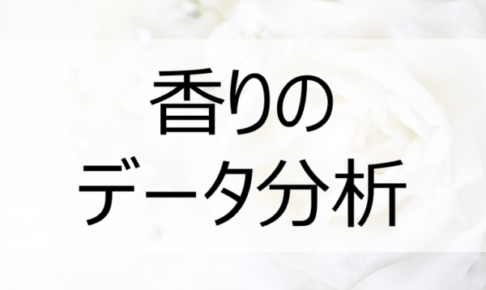


・どんな条例に基づいて必要なの?
・もし準備する場合、どれくらい準備しておくとよいの??